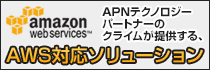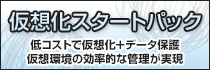きっと近い将来には、と思っていたけど、悲報は突然10月5日の夜にやってきた。
Apple社からの発表でSteveJobs氏が死去したとのテロップがニュースで流れた。
数分後にはシリコンバレーの知人達が次々にJobs関連の情報をTwitterでつぶやき始め、
1時間しないうちに、インターネット上でも大きなニュースになっていた。
夜9時過ぎには、CupertinoにあるApple本社に追悼の意をもったAppleファン、
Jobsファンが集まり、ロウソクをともしたり、献花などが自然に始まったそうだ。
翌日の昼に、Jobsが好きだった寿司屋を訪ねてみた。
大将とは15年くらい前からの付き合いで、昔の店に通っていた頃に初めてSteveの話を
聞いた。
人気でいつも行列ができている店に、SteveJobsはLarry Ellison(オラクルCEO)に
連れられて初めてきたそうだ。 行列にも普通の人と一緒に並んで待っていたそうだ。
最初はベジタリアンだったSteveだそうだが、Larryと寿司屋に通ううちに少しづつ寿司も
食べるようになり、すっかり大将のファンになっていったようだ。
しかしながら、強い個性はレストランでも相変わらずで、お勧めの魚でどんなに美味しいと
勧めても、一切手をつけなかったり、Steveのために時間をかけて準備した特別な一品を
口にしても、何かが気に入らないのかサンキューと言葉にすることは少なかったようだ。
そんなこともあり、最初は大将は気難しい客の一人だと思っていたようだが、それが新しい
店にSteveが通うようになってからは変わっていったそうだ。
会社が潰れるのではないかと噂された頃にAppleに復帰して、iPod, iTune, そしてiPhoneと
世間を変えるヒット商品を次々に発表してきたSteveをずっとカウンター越しに見て会話を
するうちに大将もSteveのことが好きになっていったそうだ。
あるときは一人でひょっこり来たり、会社の幹部を同伴できたり、はたまた貸切で会社の
パーティにお店を使うようになったり。
ある日、Steveからいつものように貸切の依頼があったので、どうするのかと思っていたら、
Steveと緊張した面持ちの幹部が現れてアルミケースを持ち込み、そこにSteveともう一人
の幹部がそれぞれの鍵をつかってケースを開けたら、なかからプロトタイプのiPhoneが
でてきた、という現場もこの寿司屋だったそうだ。
2005年のStanfrod大学の卒業式のStay Hungy, Stay Foolishの名言を残したスピーチは
あまりにも有名だが、その中でも告白された膵臓癌をきっかけに、大将はSteveの今まで
見たことのなかった家族や他の人への愛情の配慮をみるようになったという。
大将にも、カウンター越しによりいろんなことを語るようになったそうだ。
また、大将がレストラン経営の難しさをぼやいたところ、大きさは違っても経営の苦労は
どこも同じで、自分もいつも悩んでいると答えてくれたそうだ。
そんなSteveを大将が最後にみたのは、亡くなるちょうど一月くらい前の9月だったそうだ。
車椅子にて来店、久しぶりの見た目は以前よりも痩せてはいたが、眼光するどく自分の
好きなものを注文し、ゆっくり味わって食べていたそうだ。
異端児と言われたこともあるが、シリコンバレーのギーク達のあこがれ、スタートアップを
夢見る起業家の目標、まだ56歳で惜しまれてこの世を去る偉人に合掌。




 地球の裏側から伝える、企業風景、人々の生活、街の喧嘩。ハイテク社会の鼓動を伝えます。
地球の裏側から伝える、企業風景、人々の生活、街の喧嘩。ハイテク社会の鼓動を伝えます。