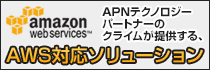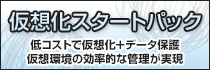クラウドを語るとき、まずセキュリティ、サービス内容、ストレージ・スペースや費用のことを考えがちである。クラウドが必要とする「資源」についてまでは考えの及ばぬことが多い。
たとえば、クラウドはどのぐらいの電気代を必要とするのだろう。これを測定するのは不可能に近い。クラウドは所有者の異なる無数のデータセンターを使用しており、データセンターの所在地や、クラウドの構成そのものさえ、あえて公表はされないのだから。
推定では、中規模の町全体に供給するに足る電力が使われていると言われる。
そして忘れてならないのは、データセンターは常にフル稼動状態でなければならないという点である。需要に応じて稼動を休止できれば良いのだが、それでは、セキュリティと機動性に悪影響が出てしまう。
それでも、クラウドの有益は声高に叫ばれており、決して一過性のものとは考えられていない。より多くの人が、より多くのアプリケーションに、格段にアクセスしやすくなったことを思えば、そこから新しいものが生まれる可能性(たとえば、医学的な新発見の可能性など)が大きく広がったと言える。
———————————————————————
(CloudTweaksコラムCan We Afford The Resources We Spend On The Cloud?より)




 地球の裏側から伝える、企業風景、人々の生活、街の喧嘩。ハイテク社会の鼓動を伝えます。
地球の裏側から伝える、企業風景、人々の生活、街の喧嘩。ハイテク社会の鼓動を伝えます。