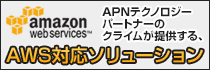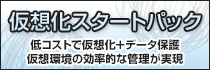今年の夏はサンフランシスコでアメリカズカップが開催された。
オリンピック47年、サッカーワールドカップより79年、全英オープンゴルフよりも9年
早く成立したスポーツ史においては最古のスポーツトロフィー、アメリカズカップを争う国際
ヨットレースである。
前回の33回大会でアメリカがカップ奪回に成功して15年振りにアメリカに戻ってきた
アメリカズカップをアメリカ側Oracle Team USAが防衛できるのか?
挑戦艇3チームから勝ち上がりルイ・ビイトン杯を手にし挑戦の権利を得た
Emirate Team New ZealandがカップをNew Zealandに持ち帰ることができるのか?
セーラーならずともサンフランシスコ市民の関心を集めた。
その結果は1勝8敗と崖っぷちのOracle Team USAが、奇跡的な8連勝をとげカップを
防衛。アメリカズカップ史に忘れられない大記録を作り大会は終了した。
その背後には大きなテクノロジーによるヨットの性能向上の戦いが繰り広げられている。
ヨットは風だけで帆走するために、ヨットのスピードを上げるにはボートの長さ、セールの
面積をできる限り大きくし、船体の水中の抵抗を減らすことが大事だが、
ボートの長さ、セール面積はルールで規定されて(開催の度に各種のルール変更や
ルール解釈の違いの紆余曲折はあったが)おり変更の自由度が少ない。
それに比べて船体の形状には自由度があり、流体力学を駆使したボディ形状の
コンピューターシュミレーションで、より速い船体形状をアメリカズカップ参加チームの間で
長く争っていた。
大きな転機は1983年、アメリカが132年間防衛し続けたアメリカズカップがオーストラリア
から挑戦したオーストラリアIIにカップが奪われた際。
オーストラリアチームがアメリカズカップ奪回に成功した後、オーストラリアIIを海上から
引き上げて海面下にあった船底を公開した際、ヨット界では大ニュースとなった。
キールと呼ばれる船底からヨット下部に突き出る錘をもつ構造体にいままで誰も見た事の
ない羽が付けられていたのだ。 この羽の形状により、風上に帆走する際の帆走性能が
著しく向上したオーストラリアIIはカップをアメリカから奪うことに成功した。
そしてもう一つの転機は2012年の第33回大会。
それまでのモノハル同士のヨット対決から、帆走性能を追求して行く中でとうとうマルチハル
対決(双胴艇のカタマランと三胴艇のトリマラン)となり、船体設計の技術競争の要素が強く
なっていった。
アメリカ側にカップ奪回をもたらしたBMW Oracle Racing 90は実に風速の2倍以上の帆走
速度で海上を帆走した。当時最速の帆走性能を引き出すために建造された船体は巨大で、
全長27m 、全高は56m。 これは世界最大の豪華客船クイーンエリザベスでもくぐれた
Golden Gate Bridgeの下をくぐれないほどの高さだった。
(余談だが、近いうちにBOR90はオラクル本社キャンパス内にある池に飾られるようで現在
準備工事中だそうです)
そして第34回大会ではAC72というボックスルールの範囲内で改造が許されたカタマランが
アメリカズカップで使われることとなった。 開催側の意図としては、船体による差が大きく
ならない範囲に規定して、セーラー同士のスキル争いに勝負の焦点を戻すことだったのか
もしれなが、同じ規定の中で各チームがシュミレーションを重ね、船体の改造をしていくなか
で、ボディから水中に突き出たダガーボートの形状を進化させたNew Zealandチームが
72Feetもある相胴艇を海面から浮上させて帆走させることに成功した。
ボディが海上に上がることによる水中から受ける抵抗の軽減は絶大で、カタマランの艇速
が飛躍的に向上した。
進化したダガーボードの名称がフォイルと呼ばれていることから、カタマランのボディが
海上に浮き上がって帆走している姿勢もフォイリングと呼ばれるようになる。
他のカップ挑戦チームも先行したNew Zealandに追いつくために、それぞれのカタマランの
フォイル形状を工夫することにより次々とフォイリングに成功、結果としてAC72は風速の
3倍以上の帆走速度を実現し、ゴールデンゲートブリッジ上の自動車の制限速度
時速45ノット以上で海上のレースコースを走り回るようになった。
フォイリングに最初に成功したNewZealandチームの船体性能の優位は絶大でアメリカズ
カップの挑戦艇を決めるルイ・ビトンカップ決勝では8レースのうち7勝(一敗は船体
トラブルによるリタイア)を上げてアメリカズカップ本戦へと進んだ。
そして開幕した本戦では、やはりNew Zealandチームが圧倒的な優位でシリーズの前半を
こなした。 スタートで多少の遅れがあっても、レースが進む間にあっという間に
Oracleチームに追いつき、そこからどんどん差をつけてしまうレース展開で、
アメリカズカップ奪回に王手をかける8勝をあげてしまった。
シリーズポイントで8対1に追いつめられていたOracleチームだが、シリーズ後半になると
船体が毎レースごとに改造されて艇速がレースごとに速くなっていった。
フォイルと呼ばれるダガーボートや水中でヨットの進む方向を決めるラダー、そしてラダーに
つけられたわずか幅20cm、長さ50cm程度の構造体のエレベーターらの形状をmm単位で
レース毎に集められた数々のデータ(風速、風向、艇速、海流、他)をもとに改造していった
結果が8連勝の大逆転、アメリカズカップの防衛へと繋がった。




 地球の裏側から伝える、企業風景、人々の生活、街の喧嘩。ハイテク社会の鼓動を伝えます。
地球の裏側から伝える、企業風景、人々の生活、街の喧嘩。ハイテク社会の鼓動を伝えます。