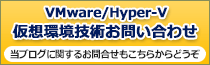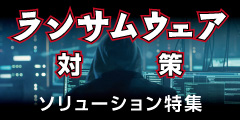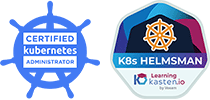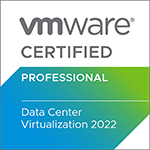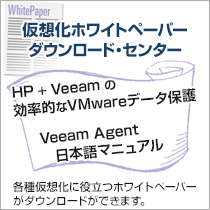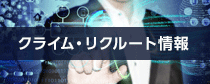データ移行とは、情報をあるシステムから別のシステムへ移動させるプロセスです。定義は単純ですが、実行は容易ではありません。準備なしに行われた移行は、ダウンタイムやデータ損失、ITチームへの多大なストレスを招く可能性があります。明確な計画はこれらのリスクを軽減し、データが正しく転送され、ダウンタイムが制御され、常に代替手段が確保されるための枠組みを提供します。
目次
データ移行計画の役割
移行計画では、移行対象、移行方法、最適なツール、結果の検証方法を明示します。単なるチェックリストではなく、異なる手法の比較、テスト移行の実施、本番環境向けの安全な経路の選択を可能にします。計画なしの移行は即興作業に陥りがちで、業務上重要なシステムにとって安全とは言えません。

移行にはいくつかの形態があり、それぞれ固有の課題があります:
- ストレージ移行 – 通常、既存のソリューションから新しいストレージソリューションまたは新しいリポジトリへの移行を意味します。ソースからターゲットへの単純なデータコピー、または組み込みのストレージ移行ツールの使用が含まれる場合があります。
- データベース移行 – 通常、既存のデータベースを同じデータベースエンジンの新しいバージョン、または別のエンジンに移行することを意味します。
- アプリケーション移行 – 通常は既存アプリケーションを異なるシステムやクラウドへ、あるいはクラウドからオンプレミス環境へ移行することを意味します。
- クラウド移行 – 企業リソースの全部または一部をクラウドへ移行することを意味します。クロスクラウド移行を含む場合もあります。
- 業務プロセス移行 – 既存の業務プロセスやワークフローを異なるプラットフォームへ移行することを意味し、通常は完全または部分的な変革を伴います。
データ移行の種類と並行して、移行の引き金となる要因を理解することが重要です。
データ移行の引き金
移行プロジェクトの引き金も同様に多様です:
- インフラ更新 – 最も一般的な移行の引き金です。物理法則上、年を重ねるごとに既存ハードウェアの故障リスクは高まり、メンテナンスに要する時間も増加します。ハードウェアのライフサイクルは通常5~7年であるため、この要因は組織に繰り返し発生します。
- 合併・買収 – インフラ更新ほど頻繁ではありませんが、確実に移行の要因となります。名称が示す通り、自組織が買収・合併される場合、あるいは他組織を買収して自社インフラに統合する場合に発生します。状況によってプロセスは異なりますが、このようなケースでは移行がほぼ確実に行われます。
- クラウドファースト戦略 – 組織が既にオンプレミスインフラを保有し、クラウドベース環境やSaaSを活用したマイクロサービスアーキテクチャへの移行により設備投資(CapEx)を削減したい場合、一般的なトリガーとなります。これは通常、インフラ更新トリガーの代替手段となります。
- コンプライアンスとデータ居住地 – 政府機関や規制対象業種への事業拡大、あるいは政府による新規規制の施行に伴い、データプライバシー等のコンプライアンス対応が必要となった場合、既存インフラの見直しと対応策の検討が求められます。これには移行が伴うことが多々あります。
- アプリケーションの近代化 – 組織が異なるソフトウェアへの移行を決定した際に通常トリガーされます。最も一般的なケースは、予算制約や特定機能の必要性から、データとワークフローを維持することを目的とした、あるCRMエンジンから別のCRMエンジンへの移行です。
データ移行計画の重要性
移行を「ただ実行するだけ」のものと扱うのは危険です。計画なしでは、本番データと事業継続性を賭けていることになります。計画は安全策となる:テスト済みのバックアップ、ロールバックオプション、明確なダウンタイム期間、成功を測定する手段を提供する。また技術・業務双方の関係者が移行内容を理解し、予期せぬ事態を減らす。
リスク軽減
計画の最重要要素はリスク軽減である。バックアップは必須だが、必要時にどれだけ迅速に復元できるかを知ることも同様に重要だ。移行計画では、手順の失敗や不整合結果発生時のロールバックを想定すべきである。
事業継続性
事業継続性も重要な考慮事項です。ゼロダウンタイム移行が不可能でも、現実的な復旧時間目標を設定し、影響が最小限となる時間帯に切り替えをスケジュールできます。
データ移行計画の構築
ソースシステムとターゲットシステムの評価
プロセスはソースシステムとターゲットシステムの両方の評価から始まります。これには互換性の確認、利用可能なツールの評価、ダウンタイムやデータ形式の問題などの潜在的な落とし穴の特定が含まれます。
範囲と目的の定義
対象を把握したら、移行の範囲と目的を定義します。移行するデータやシステム、移行の理由、成功の定義を明確にします。
移行戦略の選定
戦略とツールの選択が焦点となります。ベンダー提供の組み込みツールで対応可能な移行もあれば、サードパーティ製ソフトウェアが必要なケースもあります。タイミングも重要です:移行を業務時間内に行うか週末に実施するかによって、プロセスがもたらす混乱の度合いが大きく変わります。
バックアップ
この段階では、バックアップが最新であるだけでなく復元可能であることも確認することが重要です。多くの移行失敗は、事前にバックアップをテストしていれば回避できた可能性があります。
テスト
テストは理論と現実が交わる場です。サンドボックス環境での試行移行により互換性問題が明らかになり、計画の精緻化が図れます。これらのテスト結果を文書化することは極めて重要です。本番移行前に何が成功し、何が失敗し、何を調整すべきか明確な道筋を示すからです。テストフェーズ終了後、得られた知見を反映して計画を更新し、移行完了後に成功を確認する方法を明確にするため、最終的な検証手順を明確に定義すべきです。
検証と最適化
テストフェーズ終了後、得られた知見を反映して計画を更新し、移行完了後に成功を確認する方法を明確にするため、最終的な検証手順を明確に定義すべきです。
データ移行における一般的な課題
移行には常に課題が伴います。プラットフォーム間の連携が必ずしも円滑とは限りません。あらゆるシナリオに対応する適切なツールが存在しない場合もあります。クラウド環境間やクラウド環境内でのデータ移動時には、セキュリティ上の懸念がより深刻化します。時に最大の課題は、単に計画の不備や急ぎすぎたスケジュールであることもあります。これらの問題を完全に排除することは常に可能ではありませんが、入念な準備、反復テスト、関係者との明確なコミュニケーションにより、失敗のリスクを大幅に低減できます。
データ移行を成功させるためのベストプラクティス
移行プロセスで最も時間を要するのは準備段階です。以下に役立つベストプラクティスをいくつか紹介します:
- 明確な範囲と目標の定義 – 移行の目標を理解し、明確な範囲を定義することはプロセス全体において重要です。範囲と可能性を把握した上で準備、テスト、実行を行うことで、作業が格段に容易になります。
- 事前のデータクレンジングと検証 – 企業データには不要データ、重複データ、非アクティブデータが大量に存在するケースが一般的です。移行前にこれらをアーカイブ化し、プロセスを長引かせず、重要かつ頻繁に利用されるデータに集中しましょう。
- 移行テストの実施 – 適切なテストを完了する前に移行を実行しないでください。テスト期間の延長を躊躇しないでください。移行が失敗した理由を探すよりも、移行を確実に成功させる方が重要です。
- ビジネスと技術の両ステークホルダーを巻き込む – 主要なステークホルダーを積極的に巻き込みましょう。最終的に移行後のシステムの最大の受益者は彼らです。双方が共通言語で対話できるようにします。技術的な問題をビジネスステークホルダーと議論したり、その逆を行ったりすることは逆効果です。
- 各フェーズを文書化する – 文書化により、既に試した内容や失敗した箇所を追跡でき、将来の移行に向けたプロセスを確立できます。
- 移行後のデータ検証 – 最高クラスの移行ツールを使用した場合でも、この検証は不可欠です。移行後のデータ破損や不整合の可能性は常に存在します。移行前後のハッシュ値や特定カウンターの比較などのチェックを実施することで、データの正常な移行を確認できます。また、移行前には常に最新のバックアップを確保してください。これにより、トラブルシューティングや復旧作業に費やす膨大な時間を節約できます。
結論
移行の成功は、ツールそのものよりも準備と計画に大きく依存します。体系的なアプローチ、繰り返しテスト、慎重な検証により、データの安全な移動、許容範囲内のダウンタイム維持、ビジネスの継続的な稼働が保証されます。適切な計画を立てれば、移行は賭け事ではなく、予測可能で管理可能なプロセスとなります。
クライムはデータ移行要件にどう貢献できるか?
クライムでは各種移行ツール、サービスを国内で提供しています。


 RSSフィードを取得する
RSSフィードを取得する